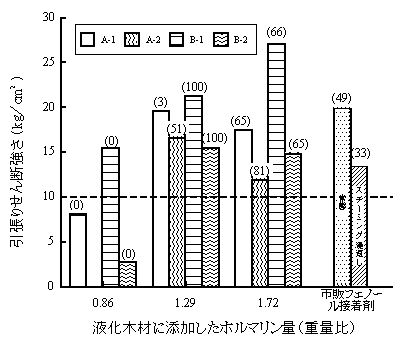
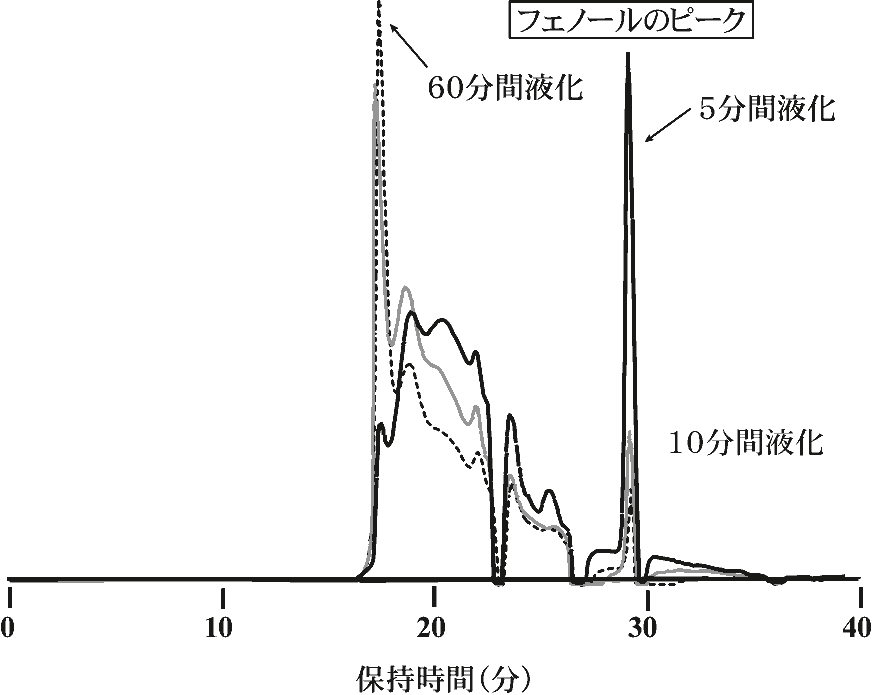
※凡例: A, Bはそれぞれ、120℃, 160℃での液化物からの試作接着剤; 後の数字は、1,常態、2,スチーミング繰返し処理後を表す。図中かっこ内は木破率。スチーミング繰返し試験適合基準: 10kg/cm2 (図中点線)。接着条件: 接着剤塗布量; 200g/m2、圧締条件; 15kg/cm2, 160℃, 6分。
※液化時間は、5分(図中、黒実線)、10分(灰色線)および60分(黒点線)。保持時間28分のピークがフェノール。木粉:フェノール=1:1(重量比)
※保持時間が短いほど高分子。
予算区分 県単 研究期間 平成8~11年度
担 当 課 製品開発課 担 当 者 鈴木 聡, 藤澤 泰士, 鷺岡 雅
県産スギ曲り材等を有効利用するための方法の一つとして、木材を液化してこれを接着剤化する技術を検討する。今年度は、フェノール液化物から接着剤を試作し、この評価と化学構造についての検討を行った。
県産スギ等をフェノール液化後接着剤化し、性能を評価した。また液化物等の化学構造について検討した。
1) 供試材:タテヤマスギ木粉(250~500μm)を使用した。また比較のためコナラおよび北洋材(エゾマツ,オウシュウアカマツ,カラマツ)を使用した。
2) 液化条件:温度とフェノール添加率を①120℃,5倍、②160℃,1倍とし、液化時間は①,②共に1時間とした。
3) フェノール液化木材から試作した接着剤の性能評価
フェノール液化木材にホルムアルデヒドを反応させて接着剤を試作し、普通・構造用合板の日本農林規格に基づいて、引張りせん断接着強さ試験(常態、スチーミング繰り返し)を行った。
4) ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)による分析
液化反応時間と未反応フェノール量の関係について簡便な測定方法としてGPCによって検討した。液化物の分子量分布についても併せて分析した。また試作した接着剤についても同様に測定した。
1) スギ材、北洋材、広葉樹材の樹種によらず、液化木材からフェノール・ホルムアルデヒド系の接着剤を合成することができた。また接着剤化する際のホルムアルデヒド添加量、および合板作製の際の圧締温度が適当であればJAS構造用合板特類の規格に適合する引張り強さを持つ合板を得ることができた(図1)。
2) GPC分析から、タテヤマスギの液化は10分以内にほぼ終了(フェノールが著しく減少)していることがわかった(図2)。このことは、液化物からの接着剤製造のコストを下げられる可能性を示している。さらに液化時間が長くなると高分子化が起きた。また、樹種による液化物の分子量分布に明らかな違いは見られなかった。試作接着剤については、ホルマリン量を1.29倍とすると未反応フェノールはほぼ消えた。
ホルムアルデヒドを使用しない接着剤の検討。
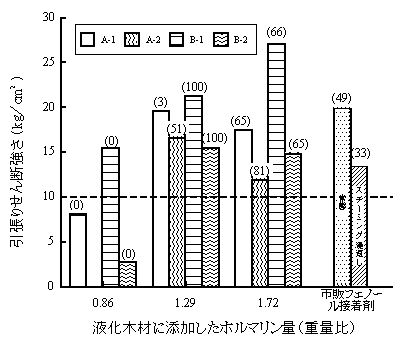 |
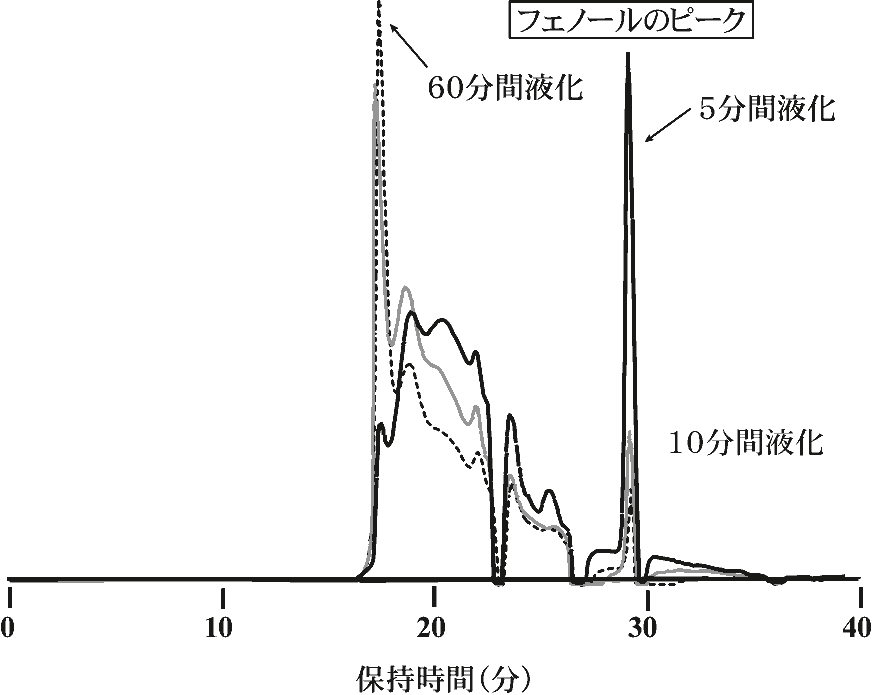 |
図1 試作した接着剤についての引張りせん断強さ
(タテヤマスギ) ※凡例: A, Bはそれぞれ、120℃, 160℃での液化物からの試作接着剤; 後の数字は、1,常態、2,スチーミング繰返し処理後を表す。図中かっこ内は木破率。スチーミング繰返し試験適合基準: 10kg/cm2 (図中点線)。接着条件: 接着剤塗布量; 200g/m2、圧締条件; 15kg/cm2, 160℃, 6分。 |
図2 フェノール液化時間を変化させた木材液化物のGPC (タテヤマスギ)※液化時間は、5分(図中、黒実線)、10分(灰色線)および60分(黒点線)。保持時間28分のピークがフェノール。木粉:フェノール=1:1(重量比) |